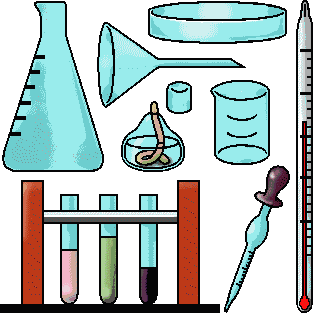 |
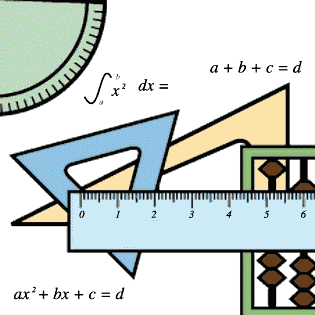 |
|
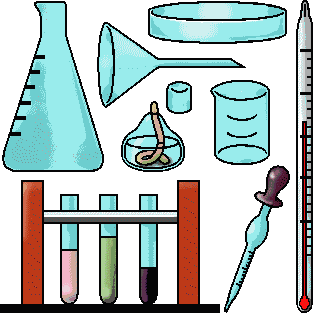 |
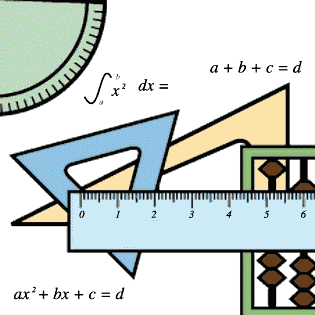 |
|
ちょっと難しいお話なので興味の無い方は、申し訳御座いませんがどうぞ、もどって下さい。
わたしは、個人的に天体や自分達も含めた宇宙に非常に興味を持ち、小学生のころには、アインシュタイン大先生の、特殊、および一般相対性理論を読んでいました。しかしながら、子供ながらに、『宇宙の果てはどうなっているのか』とか『時間はどうして流れているのか』、あるいは、『宇宙の起源と終結はどうなるのか』という疑問にとらわれ、いろんな専門書を読むに至りました。なかでも、アインシュタイン先生の相対性理論については、殆どの専門書を読破致しましたが、ニュートンの引力論を発展させたにすぎず、『事象の地平』を越えるか越えないかによって、特殊と一般の理論が別れるという事は、それを、納得させてくれる、新しい定理が無いと、どうしても理解できず、ついに、量子力学、素粒子の世界にまで足を踏み入れてしまいました。というようなわけでここに、簡単に量子力学ってどういった物なのかを引用、説明したいと思います。でも、このお勉強のおかげで、新商品の開発も行え、今となっては、ホーキング博士に何かお礼がしたいぐらいです。
素粒子と自然界の力
アリストテレスは、宇宙のすべての物質は土、空気、火、水という四つの基本的な元素でできていると信じていた。これらの元素には二つの力が働く。重さ、つまり土と水を下に沈める傾向と、軽さ、つまり空気と火を上昇させる傾向である。宇宙の内容を物質と力に分けるこのやり方は、今日でも採用されている。アリストテレスはまた、物質は連続的である、つまり一片の物質をどこまでも小さく、限りなく分割していくことができると信じていた。これ以上分割できない物質の粒にぶつかることはありえないというのである。しかし、デモクリトスのように、物質は本質的に粒状であって、すべてのものはさまざまな鍾類の、多数の原子でできていると主張したギリシア人も少数ながらいた(原子というのは、ギリシア語で"分割不可のもの"という意味である)。どちら側にもこれという証拠がないまま何世紀も論争はつづいたが、1803年、イギリスの化学者.物理学者ジョン.ドールトンは、化合物がつねに一定の比率で生成されるという事実は、原子がグループにまとめられて分子と呼ばれる単位をつくると考えることで説明できると指摘した。しかし、二学派の間の論争が原子論者に有利に決着したのは、今世紀初頭に入ってからである。その重要な物理学上の証拠の一つを提供したのがアインシュタインであった。特殊相対論に関する有名な論文の数週間前に、アインシュタインは一篇の論文を書いて、ブラウン運動と呼ばれているもの-液体中に浮いている小さな塵粒の不況則な無秩序の運動は、液体の原子が塵粒にぶつかって生じる効果として説明できることを指摘した。このころには、原子はそもそも本当に分割不可能なのかという疑問がすでに生じていた。その数年前にはケンブリッジ大学トリニティ.カレッジの評議員J.J.トムソンがすでに、電子と呼ばれる物質粒子の存在を証明していた。その電子はもっとも軽い原子の1000分の1にも満たない質量だった。トムソンが用いたのは今日のテレビのブラウン管にかなり似た装置だった。赤熱した金属線から電子が放出されるが、電子は負の電荷を帯びているので、電場をかければ、電子を蛍光塗料を塗ったスクリーンに向けて加速することができる。電子がスクリーンにぶつかると閃光が生じるのである。この電子は原子それ自体の内部から出てきたものであることがまもなく明らかになり、1911年にはイギリスの物理学者アーネスト.ラザフォードが、原子にも内部構造があることを最終的に示した。
原子は極度に小さな、正電荷を帯びた原子核と、それを取り囲むいくつかの電子でできている。彼は、放射性原子から飛びだす正電荷を帯びた粒子であるアルファ粒子が、原子にぶつかった際に進路がどのように曲げられるかを分析して、この結論を引きだしたのだった。原子核は最初、電子と、正電荷を帯びた、さまざまな数の陽子と呼ばれる粒子でできていると考えられていた。プロトンという呼び名は"第一"を意味するギリシア語に由来するが、それは、これが物質を構成する基本的な単位であると信じられていたからである。しかし1932年には、ケンブリッジのラザフォードの同僚ジェームズ.チャドウィックが、核の中にはもう一種類の、中性子と呼ばれる粒子も含まれていることを発見した。中性子は陽子とほぼ同じ質量だが、電荷を帯びていない。チャドウィックはこの発見に対してノーベル賞を授けられ、ケンブリッジ大学のゴンヴィル.アンド.カイウス.カレッジの学長に選ばれた。彼はのちに、評議員たちと意見が合わず、学長を辞任した。戦争から帰ってきた若い評議員たちが、投票によって大勢の古株の評議員を、彼らが長い間占領していたカレッジの研究室から追いだして以来、カレッジには激しい論争がつづいていた。同じような意見の食い違いがあって、やはりノーベル賞受賞者である学長ネヴィルーモットが辞任するはめになったのだった。
ほぼ20年ほど前まで、陽子と中性子は"素粒子"と考えられていたが、陽子を他の陽子あるい
は電子に高速度で衝突させる実験がなされると、これらも実はもっと小さな粒子でできていることが判明した。この小さな粒子は、カリフォルニア工科大学の物理学者マレー.ゲル=マンによって
クォークと命名されたが、彼はこの粒子の研究で1969年にノーベル賞を授けられている。なお、この名前はジェームズ.ジョイスの作品に現われる謎めいた一句、「マーク大将のために三つのクォークを!」に由来する。クオークにはいくつかの種類がある。まず、少なくとも六通りの"香り"があると考えられており、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップと名付けられている。それぞれの香りがまた、三つの"色"、赤、緑、青をもっている(強調しておかなければならないが、これらの用語は単なるラベルである。クォークは可視光の波長よりもはるかに小さく、通常の意味での色はもちえない。現代物理学者は新しい粒子や現象を命名するのに、どうやらむかしよりも想像力豊かだというにすぎない。物理学者は、もはやギリシア語にしがみついていないのだ!)。陽子あるいは中性子は一色につき一つ、計三つのクォークでできている。陽子は二つのアップ.クォークと一つのダウン.クォークを含み、中性子は二つのダウンと一つのアップを含む。他のクォーク(ストレンジ、チャーム、ボトムおよびトップ)で粒子をつくることもできるが、そのような粒子はすべてはるかに大きな質量をもち、すみやかに崩壊して陽子と中性子になる。原子も、原子の中にある陽子や中性子も、分割不可能ではないことがいまではわかっている。そこで疑問が起こる。すべてのものをつくり上げている基本的な建築用ブロックである、真の素粒子は何か?光の波長は原子の大きさにくらべてずっと長いので、普通のやり方では原子の一部を
"眺める"ことは望めない。そこで、もっと短い波長のものを使うことが必要になる。量子力学の教えるところによれば、すべての粒子は実のところ波動でもあり、粒子のエネルギーが高ければ高いほど、それに対応して波の波長は短くなる。そこで、われわれの疑問に対する最良の答えは、どれだけ高い粒子エネルギーを自由にできるかにかかっている。というのは、それによってどれだけ小さい尺度で眺められるかが決まるからである。この粒子エネルギーは通常、電子ボルトと呼ばれる単位で測られる(トムソンは電子の実験では、電場を用いて電子を加速した。1ボルトの電場から電子が得るエネルギーが1電子ボルトなのである)。人間が使い方を知っていた唯一の粒子エネルギーが、燃焼などのような化学反応で発生する数電子ボルトという低いものにすぎなかった19世紀には、原子が最小の単位と考えられていた。
ラザフォードが 実験で用いたアルファ粒子は、数百万電子ボルトというエネルギーをもっていた。もっと最近になって、われわれは電磁場を利用し、最初は何百万電子ボルトからはじまって、のちには何十億電子ボルトというエネルギーを粒子に与えるすべを知った。そのために、20年前には"素粒子"だと
考えられていたものが、実はもっと小さな粒子でできていることがわかったのである。では、もっとエネルギーが上がれば、これらもまたいっそう小さな粒子でできていることが判明するのだろうか?それは確かにありうる。しかし、われわれが自然の究極的な建築用ブロックの知識にたどりついた、あるいはそれにたいへん近づいていると信じるべき理論的理由もいくつかあるのである。
波動/粒子二重性を用いれば、宇宙のすべてのものは、光と重力も含めて、粒子という言葉を用いて記述できる。これらの粒子はスビンという性質をそなえている。スピンの一つのとらえ方は、軸を中心に自転している小さなコマのように粒子を想像することである。しかしこれは誤解を招きかねない。なぜなら、量子力学の教えるところによると、粒子ははっきり確定した軸をもちえないからだ。粒子のスピンが本当に示してくれるのは、異なる方向から見たときに粒子がどう見えるかということである。スピン0の粒子は点に似ており、どの方向から見ても同じに見える。一方、スピン1の粒子は矢印に似ていて、方向によって異なって見える。この粒子は、完全に一回転(360度)させたときにだけ同じに見える。スピン2の粒子は二つの尖端をもつ矢印に似ている。これは
半回転(180度)すると同じに見える。同じようにして、もっと大きなスピンをもつ粒子は、一回転の何分の一かで同じに見えるのである。こんなことはわかりきったことのように思えるかもしれないが、不思議なことに、完全に一
回転させても同じに見えない粒子が存在するのである。なんと、二回転させないと同じには見えないのだ!このような粒子は、1/2のスピンをもつと言われている。
宇宙の既知のあらゆる粒子は二つのグループに分けることができる。宇宙の物質をつくりあげているスピン1/2の粒子と、物質粒子間の力を生みだすスピン0、1、2の粒子である。物質粒子はいわゆるパウリの排他原理にしたがう。これはオーストリアの物理学者ヴオルフガング.パウリが一九二五年に発見したもので、この業績に対して一九四五年にノーベル賞が授けられている。彼は理論物理学者の模範だった。言い伝えによると、同じ町のどこかに彼がいるというだけで、実験は狂ってしまったそうだ! パウリの排他原理は、2つの同じような粒子は同じ状態をとることができないと述べている。つまり、この二つの粒子は、不確定性原理の課する制限の中で、位置と速度の両方が同じになることができないのである。パウリの排他原理は、物質粒子がスピン0、1、2の粒子の生みだす力の影響を受けながら、なぜ非常に高い密度の状態にまで崩壊していかないのかを説明する際に決定的に重要である。物質粒子は、仮にほとんど同じ位置にあるとすれば、かなり異なった速度をもっているはずなので、同じ位置に長くとどまっていられない。もしこの世界が排他原理なしで創造されたとすれば、クオークは別々の、はっきり確定した陽子と中性子を形づくらなかっただろう。そして、それらが電子といっしょになって別々の、はっきり確定された原子を形づくることもなかっただろう。原子はすべて崩壊して、ほぼ一様な高密度の"スープ"を形づくったことだろう。
電子その他の、スピン1/2の粒子が正しく理解されるようになったのは、一九二八年にデイラックが一つの理論を唱えてからである。彼はのちにケンブリッジ大学のルーカス記念講座教授に選出されたが、これはかつてニュートンが占めていたことのある教授職である。ディラック理論は、量子力学と特殊相対性理論のどちらとも整合性のある理論としては最初のものだった。電子がなぜスピン1/2をもつのか、言いかえれば、一回転させただけでは同じに見えないが、
二回転させると同じに見えるのはなぜか、この理論はこうしたことを数学的に説明した。この理論はまた、電子にはパートナーとなる粒子があるはずだと予測した。反電子すなわち陽電子である。一九三二年の陽電子の発見によってデイラック理論は確証され、一九三三年に彼にノーベル物理学賞をもたらした。今日では、すべての粒子には反粒子があり、いっしょに消滅しあえることがわかっている(力を運ぶ粒子の場合には、反粒子はもとの粒子自身と同じものである)。まるまる反粒子でできた反世界や反人間もありうるだろう。しかし、あなたがかりに"反自分"に会ったとしても、けっして握手をしてはいけない! そんなことをすれば、一大閃光とともにあなたがた二人は消滅してしまうだろう。なぜわれわれのまわりには、反粒子にくらべてずっと多数の粒子が存在するのかという問題はきわめて重要であり、あとの方でもう一度その話に戻ることにしよう。
量子力学では、物質粒子間の力あるいは相互作用は、すべて整数スピンすなわちスピン0、1、2の粒子によって運ばれると想定されている。どういうことが起きているかというと、電子あるいはクオークのような物質粒子が、力を担う粒子を放出しているのである。この放出の反動で物質粒子は速度が変わる。やがて力を担う粒子は別の物質粒子に衝突し、吸収される。この衝突のために第二の粒子の速度も変化し、まるで二つの物質粒子の間に力が働いたようになる。力を担う粒子がもつ一つの重要な性質は、排他原理にしたがわないことである。これは、二つの物質粒子間で交換できる粒子数に制限がなく、それゆえ強い力が生じうることを意味する。しかし、力を担う粒子の質量が大きいと、それをつくりだし、大きな距離をへだてて交換することがむずかしくなる。そのために、そのような粒子が担う力は短距離力となる。一方、力を担う粒子が質量をもたなければ、その力は長距離力になる。物質粒子の間でやりとりされる−力を担う粒子は仮想粒子と呼ばれる。"実在"粒子とは異なり粒子検出器で直接検出はできないからである。しかし、測定可能な効果が生じるので、それが存在することはわかっている。仮想粒子が、物質粒子間の力を生みだすのである。スピン0、1、2の
粒子は、ある状況のもとでは実在粒子としても存在でき、そのときには直接検出できる。その場合には、それらは古典物理学者が波と呼ぶものとして現われる。光波あるいは重力波などがそれである。このような波は、物質粒子が仮想的な力を担う粒子を交換して相互作用をする際に放出されることもある(たとえば、二つの電子の間の斥力は仮想光子の交換によるものだが、仮想光子はけっして直接には検出できない。しかし、電子がすれ違うときには実在光子が放出されることがあり、われわれはそれを光波として検出する)。
力を担う粒子は、その担っている力の強さおよびそれと相互作用する粒子にしたがって、四つの種類に大別される。強調しておかねばならないが、この四つの区別は人為的なものであり、部分理論をつくるのには便利だが、それ以上深いものには対応していないかもしれない。究極的には、四つの力すべてを、単一の力の別々な側面として説明できるような統一理論を見つけだしたいと大部分の物理学者は希望している。実際、これこそ今日の物理学の第一目標であると言えるだろう。最近、四種類の力のうち三つを統一する試みが成功した、それについて述べるとしよう。残る一種類の力、重力を統一する問題は、もっとあとに回すことにする。
四種の力のうち、まず第一にあげられるのは重力である。この力は普遍的である。つまり、あらゆる粒子が、その質量すなわちエネルギーに応じてこの力を受ける。重力は四つの力の中でもずばぬけて弱い。二つの特別な性質がなかったとすれば、われわれは重力にさっばり気づかなかっただろう。その二つの性質とは、遠距離まで作用が届くこと、それにつねに引力であるということである。このことは、たとえば地球と太陽のような二つの大きな物体の間に働く重力を考える場合、その中の個々の粒子間には非常に弱い重力しか働かなくても、全部合わさればかなりの大きさになりうることを意味する。他の三つの力は、短距離力だったり、ときには引力ときには斥力として働いて打ち消しあう傾向があったりする。重力場を量子力学的な見方で見れば、二つの物質粒子間の力は、重力子と呼ばれるスピン2の粒子が担っていると考えることができる。重力子はそれ自体の質量をもたないので、その担っている力は長距離力となる。太陽と地球の間に重力が働くのは、この二つの物体をつくり上げている粒子の間で重力子が交換されるせいである。交換される粒子は仮想的であるにもかかわらず、確かに測定可能な効果をつくりだす-地球はそれによって太陽のまわりを回っているのだ!実在重力子は古典物理学者が重力波と呼ぶものだが、波としても非常に弱いものである-そのために検出がむずかしく、いまだに観測されていない。
つぎに、電磁気力がある。これは電子やクオークのような電荷を帯びた粒子には働くが、重力子のような電荷を帯びていない粒子には作用しない。この力は重力にくらべてはるかに強い。二つの電子の間に働く電磁気力は、その間に働く重力の一億X一億X一億X一億X一億倍のさらに100
倍(1のあとにゼロが四二個つく)も大きい。しかし電荷には正と負の二種類がある。正電荷どうしの間に働く力は、負電荷どうしの間に働く力と同じく斥力であるが、正電荷と負電荷の間の力は
引力である。太陽や地球のような大きな物体は、正電荷と負電荷をほぼ同数含んでいる。そのために個々の粒子の間の引力と斥力はほぼ打ち消しあってしまい、実際の電磁気力は非常に小さくなる。しかしながら、原子や分子という小さな尺度では、支配的なのは電磁気力である。負に帯電した電子と正に帯電した原子核内の陽子の間に働く電磁気の引力が、重力が地球に太陽を回らせているのと同じように、電子に原子核のまわりを回らせているのだ。電磁気の引力は、光子と呼ばれる、スピン1で質量のない仮想的な粒子を大量に交換することで生じると考えられる。ここでは光子は仮想粒子として交換されるのである。しかし、一つの電子がある許される軌道から、原子核にもっと近い別の許される軌道に移るときには、エネルギーが解放され、実在光子が放出される、それが適当な波長をもっていれば人間の眼で可視光として観測できるし、あるいは写真フィルムのような光子検出装置で観測できる。同じように、実在光子が原子に衝突すると、原子核に近い軌道からもっと遠い軌道に電子が移ることも起こる。光子はそのためエネルギーを使い果たし、吸収されてしまう。
第三の力は弱い核力と呼ばれるものである。これは放射能にかかわりのある力であり、スピン1/2
のすべての物質粒子に作用するが、光子や重力子のようなスピン0、1、2の粒子には作用しない。
弱い核力がやっと十分理解されるようになったのは一九六七年である。この年、ロンドン大学インペリアル.カレッジのアブダス.サラムとハーヴァード大学のステイーヴン.ワインバーグの二人は、弱い核力と電磁気力を統合する理論を提唱したのだった。これはそのほぼ100年前に、マクスウェルが電気と磁気を統合したのに似ている。サラムとワインバーグは、光子以外にも、重いベクトル.ボース粒子とまとめて呼ばれるスピン1の粒子が三つあって、弱い核力を担っていると示唆した。これらはW+、W-およびZ0であって、いずれも100ギガ電子ボルト程度の質量をもっている(1ギガ電子ボルトは10億電子ボルトにあたる)。 ワインバーグ=サラム理論は、"自発的な対称性の破れ"と呼ばれる一つの性質があることを示している。これは、低エネルギーではいくつかの完全に異なった粒子に見えていたものが、実はすべて同じ型の粒子であって、ただ異なる状
態にあっただけだと判明したことを意味する。これらの粒子は高エネルギーではすべて同じようにふるまう。この効果は、ルーレット盤上の玉のふるまいにかなり似ている。高エネルギーでは(つまり盤が急速に回転しているときには)、玉はすべて本質的に一通りのふるまいしかしない-ひたすらぐるぐる回るだけだ。しかし盤の回転が遅くなると、玉のエネルギーは減少し、最後には三七個の溝のどれかに落ちこんでしまう。言いかえると、低エネルギーでは、玉がとりうる異なった状態が三七通り存在する。もしなんらかの理由で、低エネルギー状態にある玉しか観測できないとすれば、われわれは三七通りの異なる型の玉があると思いこんでしまうだろう!
ワインバーグ=サラム理論では、エネルギーが100ギガ電子ボルトをはるかに越えると、三つの新しい粒子と光子はすべて似たようなふるまいを示すようになる。しかし通常の状況で見られる、
もっと低い粒子エネルギーでは、粒子間のこの対称性は破れてしまう。W+、W-とZ0は大きな質量を獲得し、その担っている力の到達範囲は短くなってしまうだろう。この理論をサラムとワインバーグが提唱したとき、信じた人は少なかったし、加速器はW+、W-町あるいはZ0粒子をつくりだすには出力が足りなかった。しかし、その後10年かそこらのうちに、低エネルギー状態についてこの理論が行なった他の予測が実験にたいへんよく合致したので、サラムとワインバーグは一九七九年
にシェルドン.グラショウとともにノーベル物理学賞を獲けられた。グラショウもやはりハーヴァード大学におり、電磁気力と弱い核力について似たような統一理論を唱えていた。誤ってノーベル賞を与えたのではないかというノーベル委員会の心配は、一九八三年に解消された。まさに予測通りの質量その他の性質を備えた、光子の三つの重い仲間が、CERN(ヨーロッパ合同原子核研究機構)で発見されたのである。この発見にたずさわった数百人の物理学者チームを率いたカルロ.ルビアは、実験に用いられた反物質貯蔵システムを開発したCERNの技術者シモン.ファン.デル.メールとともに一九八四年度のノーベル賞に輝いた(今日では、すでに頂点に登りつめているのでないかぎり、実験物理学で名を上げることはむずかしい!)。
第四の力は、陽子と中性子の中でクオークをまとめており、原子核の中で陽子と中性子をまとめている、強い核力である。この力はもう一種のスピン1の粒子が担っていると信じられている。これはグルーオンと呼ばれるもので、自分自身およびクオークとしか相互作用しない。強い核力には "閉じこめ"という奇妙な性質がある。つまり、この力は粒子を結びつける際に、つねに色がなくなるような組み合わせ方をするのである。クオークは単独では取りだせない。赤、緑あるいほ青の色があるからだ。赤のクオークは単独でいるかわりに、グルーオンの"ひも"によって緑と青のクオークと結びつく(赤+録+青=白)。このような三つ組が陽子あるいは中性子を構成する。粒子を白くする可能性はもう一つある。それはクオークと反クオークの対である(赤+反赤、あるいは 録+反緑、あるいは青+反青=白)。このような組み合わせで形づくられるのがいわゆる中間子だが、これは不安定なものだ。クオークと反クオークはたがいに消滅しあって、電子その他の粒子をつくるからである。これに似た理由で、閉じこめのためにグルーオンも単独では現われない。グルーオンには色があるからだ。グルーオンは単独で現われるかわりに、全体として白色に見えるような集団をつくる。このような集団がグルー.ボールと呼ばれる不安定粒子である。 閉じこめられているために、孤立したクオ−クやグルーオンが観測できないということになると、クオークとグルーオンという粒子が存在するという考えそのものが、いささか形而上学的なものに見えかねない。しかし、強い核力には漸近的自由性と呼ばれるもう一つの性質があって、そのためにクオークとグルーオンの概念ははっきり確立されているのである。通常のエネルギー状態では強い核力は確かに強く、クオークどうしを固く結びつけている。しかし、巨大な粒子加速器で実験してみると、高エネルギーでは強い核力はずっと弱くなっており、クオークとグルーオンがほとんど自由粒子のようにふるまっていることがわかる。
電磁気力と弱い核力の統合が成功したことに刺激されて、この二つの力と強い核力を結びつける、いわゆる大統一理論(GUT)の試みもいくつかなされた。この名称はいささか誇張ではある。重力が含まれていないのだから、大と名乗るほどの理論ではないし、完全な統一でもない。それに、理論として完璧だとも言えない。というのは、理論からは値が予測できず、実験に合うように選ぶしかないパラメーターがいくつか含まれているからである。とはいえ、これは完全な、統一された理論へのステップとなりうる。GUTの基本的な考えはこうである。まず、前に述べたように強い核力は高エネルギーでは弱くなる。一方、電磁気力と弱い核力は漸近的に自由にはならず、高エネルギーで強くなる。そのために、大統一エネルギーと呼ばれるある非常に高いエネルギーでは、この三つの力はすべて同じ強さになり、単一の力の異なる側面に他ならなくなる。GUTはまた、クオークと電子のような、共通のスピン1/2をもつ異種の物質粒子もこのエネルギーではやはり本質的に同じになることを予沸測し、それによってもう一つの統合を達成しようとするのである。大統一エネルギーの値は正確に知られているわけではないが、たぶん少なくとも1000兆ギガ電子ボルトには達しているはずだ。現在の粒子加速器は粒子をはぼ100ギガ電子ボルトのエネルギーで衝突させることができるし、計画中のものはこのエネルギーを数千ギガ電子ボルトまで上げるだろう。しかし、粒子を大統一エネルギーまで加速できるような強力な加速器は、太陽系と同じぐらいの大きさになるはずだ。現在の経済事情ではその費用はとても得られそうにない。したがって、大統一理論を実験室内で直接検証するのは不可能である。しかし、電磁気力と弱い核力の場合と同じように、この理論からも、低エネルギーでも検証可能な帰結が引きだせる。その中でとくに興味深いのは、通常の物質の質量の大部分を占めている陽子が自発的に崩壊して、反電子のようなより軽い粒子になるという予測である。これが可能なのは、大統一エネルギーのもとではクオークと反電子との間には本質的な違いがなくなるからだ。陽子の内部にある三つのクオークは通常、反電子に変わるのに十分なエネルギーをもっていないのだが、ごくまれにクオークの中の一つが遷移を起こすに足るエネルギーを得ることがある。これは、不確定性原理のために、陽子の中のクオークのエネルギーが厳密に固定されないからである。この変化が起これば陽子は崩壊するだろう。
クオークが十分なエネルギーを得る確率はきわめて小さいので、少なくとも一億X一億X一億X100万年(1のあとにゼロが30個つく)ぐらい待たなくてはそのような現象は見られない。これはたった100億年かそこらしかないビッグバン以来の時間にくらべて、はるかに長い時間である。ということになると、陽子の自発的崩壊の可能性は、とても実験的には検証できないように思えるかもしれない。しかし、非常に多数の陽子を含む大量の物質を観測すれば、崩壊を検出する機会は増やせる(たとえば1のあとにゼロが31個つづくような数の陽子を一年間観測した場合、もっとも簡略なかたちの大統一理論にしたがえば、一個以上の陽子崩壊が観測できるだろう)。このような実験はいくつか試みられているが、陽子あるいは中性子がこのやり方で崩壊するという確実な証拠はまだ得られていない。実験の一つはオハイオのモートン岩塩坑の中で行なわれ、8000トンの水が用いられた(深い坑道の奥で実験されたのは、宇宙線のために陽子崩壊とまぎらわしい現象が引き起こされるのを避けるためである)。実験期間中、自発的な陽子崩壊が観測されなかったことから、陽子の予想される寿命は一億X一億X一億X1000万年)1のあとに0が三 一個つく)以上であると計算できる。これはもっとも簡単な大統一理論が予測する寿命よりも長いが、もっと複雑な理論はより長い寿命を予測している。それを検証するには、さらに大量の物質を用いて、もっと緻密な実験を行なわなければならないだろう。
自発的な陽子崩壊を観測することが非常にむずかしいとはいっても、われわれの存在自体がその通過程の産物であるかもしれないのだ。その逆過程とは、クオークが反クオークにくらべてけっして多くはなかった初期の状況から、陽子-もっと簡単に言えばクオーク-が生じる過程であるが、このような初期状況は宇宙のはじまりとしてはもっとも自然な考え方である。地球上の物質は主として陽子と中性子でできているが、これらの粒子はもともとクオークでできている。反クオークでできた反陽子あるいは反中性子は、物理学者が大型の粒子加速器でつくりだした少数のものを除けば、存在していない。わが銀河のすべての物質についても同じことが言えるという証拠が宇宙線から得られている。高エネルギー衝突で粒子/反粒子対としてつくりだされる少数のものを別にすれば、反陽子も反中性子も存在していない。もしわが銀河に大きな反物質の領域があるとすれば、物質領域と反物質領域の境界あたりから大量の放射が観測されると期待していい。そこでは多数の粒子が反粒子と衝突して、たがいに消滅しあって高いエネルギーを放っているはずだからだ。他の銀河の中の物質が陽子と中性子でできているのか、反陽子と反中性子でできているのかについては直接的な証拠はないが、そのどちらかであるはずだ。一つの銀河の中でこの両者が混在していることはない。混在している場合には、やはり消滅から生じる大量の放射が観測されているはずだからだ。したがって、すべての銀河は反クオークではなくクオークでできているものと信じられている。ある銀河が物質であり、ある銀河が反物質であるということはありそうもないように思われる。なぜ反クオークにくらべて、クオークがこれほど多いのか?なぜ同じ数だけ存在していないのか?数が等しくないことが、われわれにとって幸運だったことは確かである。なぜなら、もし数が同じだったとすれば、はとんどすべてのクオークと反クオークが初期の宇宙でたがいに消滅しあってしまい、放射で満ちてはいるが、物質はほとんど存在しない宇宙が残されるからだ。そこには銀河も恒星もなく、人間の生命が発展すべき惑星もなかっただろう。幸いなことに、なぜ宇宙が同数のクオークと反クオークから出発しながら、現在反クオークよりも多数のクオークを含むようになっているのかという問題について、大統一理論が一つの説明を提供するかもしれない。すでに見てきたように、GETによれば、クオークは高エネルギーで反電子に変わることができる。その逆過程、つまり反クオークが電子に変わることも、電子と反電子が反クオークとクオークに変わることも許されている。
ごく初期の宇宙には、粒子エネルギーがこのような変換を起こせるほど高かった、高温の時期があった。でも、なぜその結果クオークが反クオークよりも多くなるのか?その理由はこうだ。クオークと反クォークとでは、物理法則がまったく同じではないのである。一九五六年までは、物理法則は、C,P,Tと呼ばれる三つの別々な対称性のいずれにもしたがっていると信じられていた。対称性Cとは、粒子にも反粒子にも同一の法則が働くことを意味する。対称性Pは、いかなる状況とその鏡像についても法則が同一であることを意味する(右回りに自転している粒子の鏡像は左回りに自転している粒子である)。対称性Tは、すべての粒子と反粒子の運動の向きを逆にすれば、系はそれ以前にあった状態に戻ることを意味する。言いかえると、時間の前向きの方向でも後向きの方向でも、働く法則は同一なのである。一九五六年、アメリカの二人の科学者リー.ツンタオ(李政道)とヤン.チンニン(楊振寧)は、弱い力は対称性Pにしたがっていないと唱えた。別の言葉で言えば、弱い力は宇宙の鏡像が発展するのとは異なるかたちで、宇宙を発展させるのである。同僚のウー.チェンシュン(呉建雄)はその年のうちに、二人の予測が正しかったことを証明した。ウー女史は、放射性原子の核を磁場の中にならべて、すべてを同じ方向に自転するようにそろえ、電子がある方向には他の方向よりも多く放出されることを示して、予測を証明したのだった。その翌年リーとヤンには、この考え方を打ちだしたことに対してノーベル賞が授けられた。また、弱い力は対称性Cにもしたがわないことも見いだされた。つまり、弱い力のために、反粒子で構成された宇宙はわれわれの宇宙とは異なったようにふるまうことになる。にもかかわらず、弱い力は二つの対称性を結びつけた対称性CPにはしたがっているように見えた。これは、かりに宇宙のすべての粒子をその反粒子と入れかえてやれば、宇宙はその鏡像と同じように発展するだろうということである!しかし一九六四年には、もう二人のアメリカ人J.W.クローニンとヴァル.フィッチが、K中間子と呼ばれる粒子の崩壊は、CP対称性にさえしたがっていないことを発見した。クローニンとフィッチはこの研究で一九八〇年にノーベル賞を受けた
(宇宙はわれわれが考えていたほど単純ではないことを示したことに対して、多数の賞が授けられたのである!)。ある数学的な定理から、量子力学と相対論にしたがう理論は、組み合わされた対称性CPTにつねにしたがわなければならない。言いかえると、粒子を反粒子で置きかえ、その鏡像をつくり、さらに時間の向きを逆にすれば、宇宙は同じようにふるまうだろう。だが、クローニンとフィッチが示したように、粒子を反粒子で置きかえ、その鏡像をつくっても、時間の向きを逆にしなければ、
宇宙は同じようにはふるまわない。したがって、時間の向きを逆にすれば物理法則は変わるはずである-対称性Tにしたがわないのである。確かに初期の宇宙は対称性Tにしたがっていない。時間が前向きに進むにつれて宇宙は膨張する
-時間が後向きに進んだら宇宙は収縮するだろう。そして、対称性Tにしたがわない力が存在するために、宇宙が膨張するにつれて、電子が反クオークに変わるよりもさらに多数の反電子がクオークに変わることができたのである。やがて宇宙が膨張して冷えていくと、反クオークはクオークと消滅しあうようになるが、反クオークよりもクオークの方が多いので、少数のよぶんなクオークが残ることになったのであろう。われわれが今日見ている物質を形づくっているのはこれらのクオークであり、われわれ自身もそれでできている。このように、われわれの存在それ自体も、定性的なものにすぎないとはいえ、大統一理論の一つの確証と見なすことができるのである。消滅しあったのちに残るクオークの数が予測できない点、あるいは残るのがクオークなのか反クオークなのかさえ予測できない点には、不確定さが存在している(もっとも、反クオークが余ったとしても、われわれは反クオークをクオーク、クオークを反クオークと命名しなおすだけのことだが)。大統一理論には重力が含められていないが、このことはたいした問題ではない。重力はごく弱い力なので、素粒子あるいは原子を扱っているときには、その効果はふつう無視できるからである。しかし重力が長距離力であり、つねに引力であることは、重力の効果がすべて積み上げられていくことを意味する。そのため、十分な数の物質粒子があれば、重力は他のすべての力を圧倒することができる。重力が宇宙の進化を決定しているのはこのためである。恒星程度の大きさの物体でさえ、重力の引力は他のすべての力に打ち勝って、星の崩壊を引き起こすことができる。一般的な物理学者の一九七〇年代の研究は、このような恒星の崩壊から生じるブラックホールと、そのまわりの強力な重力場に焦点を合わせていた。